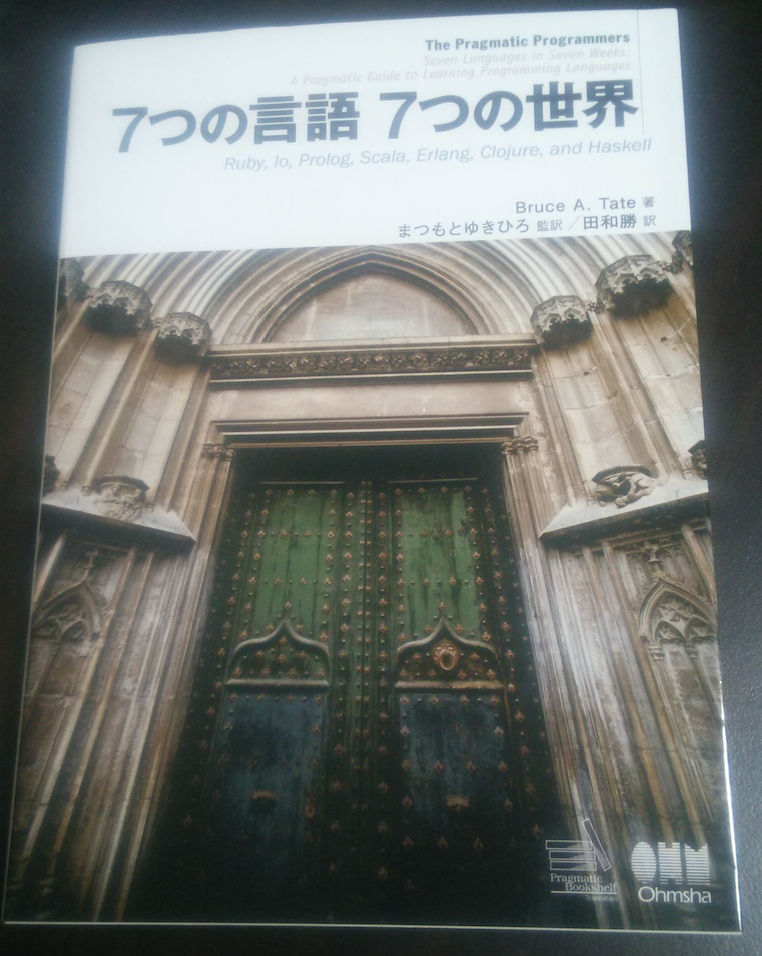一人が全員から集めた付箋をみて、集計し書き出しました。 付箋は破ってゴミ箱に捨てることにより、誰がどの立場かはわからないけど、どういう人がどれくらいいる事実だけはわかっています。
結果を見てみると、想像していた通りではなく、ズレすぎず、面白かったです。 この場をどうしていくかの指標になりました。
2つ目: 何をすべきか決定するアクティビティ 「質問の輪」
次のアクティビはこの場で「何をすべきか決定する」です。 今回の場では洗い出しを行うつもりはもともとなかったので、感情・想いをベースに話を進めたり、均等に考えを引き出すことに重きをおきました。
このアクティビは、「次のイテレーションにおける試みやアクションステップをチームが選びやすいようにする。特にチームメンバーがお互いの意見を聞く時に使用するとよい」そうです。
私たちにぴったりです!!
ファシリテーターをおかず、均等に発言したり声の大小にかかわらず、しゃべる・聞くということがテンポよく、うまくできるという仕組みです。
やり方は簡単 質問に答えて質問をするだけ
円になって座り、最初の回答者を決めて「次のイテレーションで取り組みたいことはなんですか?」の質問に自身の考えを述べてもらいます。 これまでのやりとりを踏まえたうえで、自身の考えを述べて、さらに次の人に質問をするという流れです。これを2周くらいすれば、質問がブラッシュアップ・深掘りされて、気づけばいい感じにアクションが具体化と合意に近づいていきます。
どうだった?
ESVPの流れから、私たちがこういう状況にあることをどう思うか?から始まり、実はお互いが状況に応じて補完しあえる関係にあって、バランスよく活動できていることを知ることができました。 話題が自然と落ち着いていき、他人の考えやスタンスを知れることによる、心のゆとりや今後も続けていくことの障害がないことがわかったのです。
長いことやっていると人の参画・移動に関する話もあがって、そこのあたりの考えも知れて良かったです。 毎回だと窮屈になってしまうかもしれないと思いましたが、たまにこういう形でやるといいですね。 非常に生産的に話が進んでいった気がしました。
3つ目: レトロスペクティブを終了するアクティビティ 「感謝」
「ポジティブにイテーレションやレトロスペクティブを終える」目的に利用できるそうです。 長い期間やっていると日々あったこと、心に思っていたことをあらためて感謝の意を込めて感謝を伝えられるのははうれしいものです。
感謝することは任意で、誰も話さない時間がきたら終わるという、実施方法となります。
自然とでる言葉たち
この業務に関わっている人全員が、主たる業務というわけではなく、時間を確保をして協力しながら活動を進めています。 時には個々人が主たる業務のピークがきて、動きが鈍くなってしまう時もあります。 そういう時に誰かが主体的にやってくれたことはよく覚えていて、感謝の言葉が出ることが多かったです。
不思議なものですよね。自分がやった時のことは覚えていないのに、やってもらった行為はよく覚えているというのは・・・
このレトロスペクティブをとおして
終わってみると、普段よくやっている
などでおこなう「データの収集」「アイディア出し」「何をすべきか決定する」とは違うアクティビティで、終わった時の気持ちの感覚も独特のものがありました。求められていること・貢献したいこと・状況が変わることによって、立場を表明して立ち去ったり新陳代謝するは必要だと考えています。そういう時に、「いい意味でうまくできそうだな」という手応えが掴めました。自分たちが、なぜこの場にいるのか、考え続けたりやり方を工夫することの大事さをあらためて感じられました!
1時間30分があっという間で、いい時間を過ごせたと思うので、応用して他の場でも色々なアクティビティを選んで使ってみたいなと思いました。